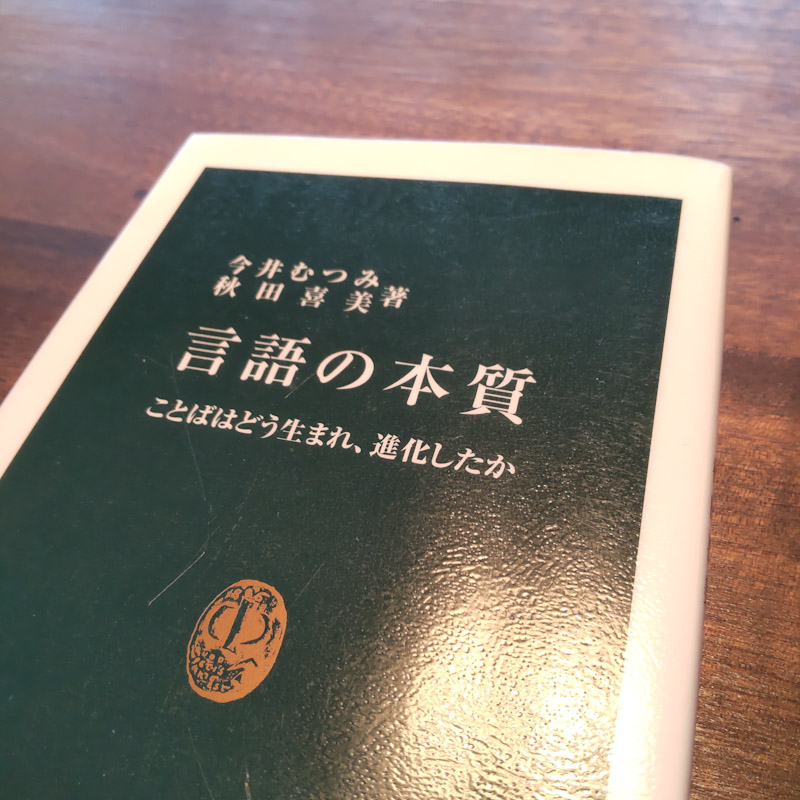
AIは言葉を理解できるのか?
chatGPTをはじめとした最近話題のAIでは、言葉を理解しているわけじゃない。単に語順を推測しているだけ。なんて聞きます。
じゃなぜAIは言葉を理解できないの?私にはいまいちピンとこなかったんです。そこでこの本を読んでみたら、なんとなく感覚的に分かったうえに、すごく面白かったです。
言葉とは何か
さて最初はこの本、「言葉の記号性」について説明が始まります。そんなこと言われたって、なんのことかわかりませんよね。もう少し噛み砕くと…
まず、言葉はどこまで行っても言葉です。あたりまえ。僕らの頭の中にあるイメージの、一部を表現しているに過ぎない。どんなにしゃべりが得意な人だって、イメージしていること全てを言葉で正しく伝えるというのは、仕組みとして無理。
受け取り手がどう解釈するか、という問題だって大きいし、それ以前に、言葉にした時点で情報量が激減してるんだもの。
モノクロ写真がどんなに頑張ったって、カラー写真に情報量では勝てないでしょ。そのカラー写真だって、僕らの目や心に映った景色よりは、情報量落ちてるわけで。ここはどうしようもない。
皆さんも、仕事で「そういう意味で言ったのではありません!」とか「そんな意味で言われてるとは思わなかった」なんて、よく言いませんか。私はしょっちゅうです。
じゃなぜ言葉を使うのか
そんな不便な、行き違いがありまくりの言葉。なんでそんなもの使うんだ?
ここがまた面白いところなのですが、情報量を落としてまで「言葉」に閉じ込めて伝えると、それはそれで良い点もあるわけです。例えばこんなことですね。
- イマ・ココを超越できる
- 誰にでも伝わる
- 伝える効率がいい
ここ、もう少し説明を加えましょう。
イマ・ココを超越できる
言葉を使うと、いま、目の前にあるもの 以外を表現したり、伝えたりすることができる。
「リンゴが食べたいなあ」と言ったら、目の前にリンゴがなくても、何したいか伝わるわけです。これはなかなか大事ですが、言われてみないと気づかない。他の動物は、「オオカミが来たぞ!」とかの鳴き声は持っているけど、「あいつに会ったらよろしく言っておいて」みたいなことは、無理なわけです。たぶん。
誰にでも伝わる
あうんの呼吸なんて言いますけど、いつも会っている人なら、言葉にしなくても意図が伝わることはある。でも、言葉を使えば、初対面の人にすら、意図を伝えることができる。逆に言えば、言葉が違う人、つまり外国人には伝えられない。
伝える効率がいい
何かを伝えようと思ったら、言葉以外の手段も沢山あります。身振り手振り、表情などもあるし、絵をかいても良い。でも言葉なら、短時間で簡単に、まあまあの情報伝達ができる。絵を描くよりずっと効率がいいわけです。
知らない人とも協力し、大きな社会を形成し、それによって生き残っていく人類。効率のいいコミュニケーション手段というのは、絶対必要なわけです。多少の行き違いがあったとしても、それより良いコミュニケーション手段がないじゃない。というわけですね。
言葉が理解できないとはどういうことか
じゃ言葉で伝えれば良いのか。そうかそうか。言葉って便利だね。なんて思ってしまいそうになりますが、ちょっと待って欲しい。言葉で伝えられても、全くわからないことありますよね。
私自身で言えば「エモい」という言葉。使われだしてから何年も目にしていますが、いまだにピンと来ません。
言葉の解説を何度読んでも、「あぁ、そういうことね」と思えない。
この状態を専門的には、「接地されていない」と言うらしいです。「エモい」という記号が私の感覚に結び付いていない。
そしてこれこそが俗にいう「記号接地問題」。AIが言葉を理解できない根本的な原因。だってAIには感覚も体験もないから。
というわけで、AIが言葉を理解できない という状態は、我々も疑似的にイメージできるわけです。
ヤバいとか、エモいとか、ぴえんとか、ぱおんとか、なんやかんや、あるでしょ?おっさんならば。
理解の手助けになる仕組み
さて、言語を真に理解するにあたり必要な「記号接地」まで、お話できました。
しかし、それじゃ赤ちゃんはどうやって言葉を習得するんだ。言葉というものの存在を知らない状態の赤ちゃんは「そういうことか!」ってひらめかない限り、言葉が習得できないことになります。
そこで「わざわざ接地しなくても、なんとなく接地できてる言葉」が登場します。それはオノマトペ。擬音語とか擬態語です。ここに着目するのが、本書の面白いところ。
たとえば私が何かを食べて「ふぁいふぁいな味がした」と言ったとします。そんな言葉はないですが、どんな感じか、なんとなく分かるのではないでしょうか。少なくとも、辛いわけじゃないだろう。と思いませんか。知らない言葉でも、なんとなく分かる。
こういうところをヒントに、赤ちゃんは「言葉でこの世界を表現する」ことに気づき、身の回りの世界と言葉を結び付けてとらえ始める。そうなったらあとは、文法とか、語彙とかを充実させるだけの問題です。はじめの一歩だけ気づけば、あとはうまく回りだす。そのためにオノマトペがある。
もちろん、これは学説のひとつであり、絶対的真実かどうかわかりません。ただ、こんな考察と実験を積み重ねながら、結局言葉とは何なんだ という考察を進めるのもなかなか面白い。この本はひとつひとつの論がわかりやすく書いてあるので、読んでいるうちに自分の中でも考えが進み、これも面白い読書体験となります。
「AIも人間も結局、推論をもとに言葉を扱っているんだなあ」とか、「AI(LLM)は帰納的推論をしていて、人間はアブダクション推論をしているだけなのかな」とか。
そんなわけで、なんだかグダグダなレビューになってしまいましたが、中身は読んでもらうとして、この本の面白さだけ伝われば嬉しいです。伝わるんかしら。
とにかくお勧めです。この本。一部で話題になってるだけのことはありました。
